フォロワーさんのツイートを見て国語の授業の進め方を提案したので、まとめます。
個別や家庭教師の先生に進め方をお願いするときの参考になれば幸いです
はじめに
元ツイート
フォロワーさん国語個別の検討がTLに流れてきたので、受講する時のアドバイスを。
「指定された問題を家庭で演習→塾で先生から解説を受ける」この方式は演習量確保の効果はありますが、読解力を上げる効果に乏しく、読解が苦手な場合は…効果はほとんどありません。
じゃあ、どうすれば良いの…(続く)— そうちゃ@受験図解講師for2022&2023&2024年受験組 (@zky_tutor) January 17, 2021
結論から言うと、
「家で演習→塾で解説」ではなく
「塾で読み方解き方を説明→家で演習→塾では簡単なチェックだけ行う」という提案です。
「読み方解き方」は国語の公式の事です。説明文の読解公式はコチラ。物語文の読解公式はコチラ
この後、順を追って書いていきます。
国語学習の特徴と問題
学習と解答の過程
国語の授業を受けても国語が分かった!とか国語が出来るようになった!というのは少ないと思います。それに対して、同じような授業形式で多少は効果があると思われる算数を例に、学習してから解答するまでの過程を考えてみましょう。
A:問題を解く前に(例題等を用いて)抽象的ルール(公式/解法)を学習・理解・記憶する
B:出題された問題文の情報(数値/条件など)を抽出する。
C:適用すべき公式/解法を選択/構成する
D:Bで抽出した情報をCの公式/解法にあてはめ計算処理して解答を導く。
このような流れになっていますね。そして国語もこれと同じ過程をたどると私は考えています。
国語の「授業」の問題点
国語と算数の違い
ただ、国語ではA→B→C→Dとたどるのが算数よりも難しいのです。
過程A(抽象的ルールの学習理解)
算数ではテキストの体系に沿って各章のはじめに定理や公式が明示されるが、国語では「段落に気をつけよう」「気持ちを読み取ろう」等の断片的な読解/解答の公式が散発的に書いてあるだけで、体系は全く分からない。
過程B(問題文の情報抽出)
算数の問題文は公式にあてはめる情報のみで出来ていて余分な情報は無いので抽出が簡単です。
それに対して、国語では余分な情報が混じっています。特に説明文では半分以上が処理に使わない情報なので抽出を行う能力が必要になります。
ところが国語では読解公式(抽出の方法)が明らかになっていないので、生徒さんはどのように必要な抽出すれば良いかよく分かりません。
このように学習から解答に至る過程の前半部分で国語は算数より難しいのです。
授業効果の違い
算数の授業は
「(公式知ってるね?)(問題の数値/条件分かったね?)この問題ではあの公式を適用して、こうやって計算します」
と過程CD(公式に問題文から抽出した情報を公式にあてはめて解答する)の補助として成立しえます。
それに対して、国語の授業は
「(…公式は示されない…)(…情報抽出のやり方を見せない…)この文章ではここにこう書いてあるから、答えはこうなります」
という他の文章には通じない単なる「答え合わせ」になってしまうのです。
単なる答え合わせを聞かされても、国語が苦手な生徒が得意になることは少ないですね。
これが国語の授業を聞いても出来るようにならない理由です。
国語の授業の理想形
ここまでの話を踏まえると、国語が苦手な生徒が個別/家庭教師で授業を受ける際に望ましい授業形式も決まります。
もう一度「学習解答過程(A~D)」を示します。
A(事前に)抽象的ルール(公式/解法)を学習
B出題された問題文から情報(数値/条件)を抽出整理
C適用すべき公式/解法を選択/構成する
D公式/解法にあてはめ計算処理
この各過程ごとに授業ですべきことを決めていきます。
読解・解答の公式学習
A(事前に)読解と解答のルールを公式として記憶させる
授業では国語の読解/解答体系に沿って、読解と解答のルールを説明し、理解・記憶させる必要があります。
(この体系は講師・テキストによって異なるだろうし、そもそも体系を「持っていない」知らない」講師が大半だと思うので、例えば担当の講師に私のサイトを見せて「これを参考に」とお願いしても良いでしょう。)
読解ルールは文章のジャンル(説明/物語)で異なるので、より苦手なジャンルを選択して1ヶ月以上集中的に継続するのが良いでしょう。
そして読解ルールと並行して、宿題を解くのに必要な解答技法(記号問題の消去法など)も教える必要があります。
そうちゃ式の「解答技法まとめ」
これらの習った公式(読み方/解き方)は保管して復習できるようにして下さい。宿題として記憶を宿題にします。
((板書をそのまま暗記プリントにしたノートの一部。下を隠して記憶します))
((単語カードにした例。表に問題、裏に答え))
問題文からの情報抽出と整理
B本文中の重要な箇所を(Aに含まれる)基準で取捨選択(線引き等)整理(構造把握)する過程を示す。
例えば私の体系では説明文は➀テーマと主張(QA)➁主張と反対意見の対立(BA)➂主張内の対比(ab)を読み取る、これらの要素は抽象的である、と定義します。
この定義にしたがって、説明文の問題文を「抽象的な記述」と「具体的な記述」に区別していくのが情報抽出の第一歩になります。
また、物語文を私の体系では ➀背景・人物の設定 ➁人物の感情の変化 ➂人物間の感情の変化 を読み取ると定義します。
この定義にしたがって、物語文の問題文を「設定に関する情報」「感情に関する情報」「関係に関する情報」のいずれかに振り分ける(または図を書いたりメモしたり)のが情報抽出の第一歩になります。
例題としての問題文を題材に、これらの情報抽出を行います。情報抽出というと難しそうですが、問題文への「線引き」や書き込み・メモ・図を書くなどの作業です。
線引きについては「解答技法のまとめ」内の「線を引く箇所」を見て下さい。
また文章問題・過去問に解答する際には選択肢の情報を抽出(線引きなど)する必要もありますね。
ここまでの段階で、文章や文章問題の本文と設問に線が引かれたり書き込みがしてある状態になっています。
残りを宿題にする
残りのC公式選択とD解答作業を宿題にする
以上のように、読解と解答のルール(公式)を教えて、それに沿った情報抽出(線引き・メモ等)を例題相当の文章に行ったら、残りを宿題にします。
つまり問題文(と設問)に書き込みなどをした問題を自宅で解いてくるのが宿題になります。
C公式/解法選択とD解答処理を宿題にするのは、A公式/解法の理解/記憶を正しく行い、B問題文の情報取捨選択を(一緒に)行って線引き等の形に残せば(算数の単元学習で公式教わった直後に例題解くのと同じで)、C公式選択はほぼ終了しているし、Dで的はずれな答えを導く可能性は低いからです。
また、不正解だったり記述が書けない場合も、ABの作業をきちんと行っていれば、簡略な解答解説を見ても理解できることが(自分が教えた経験上では)多かったです。
小まとめ
ここまでを整理すると
従来の形式:家庭で演習→授業で解説
今回の提案:授業で公式/技法解説と問題文への線引き書き込み→家庭で続きの解答を行う
となる。
実施上の問題点
授業で公式/技法解説と問題文の線引き→家庭で演習
とする場合に生じるだろう疑問点をあげると…
➀公式て何?教える順番は?量は?時間は?
②問題文は何使うの?線引くだけ?
➂宿題は採点しないの?他の宿題は?
これらについて書いてみます
公式について
国語の公式/技法は多岐に渡るので、その日の作業に必要な範囲だけをピックアップして行います。
例えば最初の授業は「線の引き方の公式」の一部(形式的に出来る作業)を説明してから、実際の文章に線を引くのを見せながら理解させて終了でしょう。
回数を進めながら公式を増やしていきます。
読解公式は姉妹サイト「そうちゃ式 国語」内の「説明文の読解公式」や「物語文の読解公式」を、解答技法は「解答技法まとめ」を参考にして下さい。
優しい過去問が解ける段階まで読解公式と解答技法を説明・理解・定着させるのには結構時間がかかります(2ヶ月くらい?)が、一度説明して復習素材にして記憶を宿題にしておけば、重ねての説明は不要なので、そこまでが我慢の時期になります。
「公式?そんなのありません」という講師が多いと思うので(汗)、「例えば、この記事みたいな…解き方を教えて下さい」と言えばよいかと思います。
それでもキチンとルールを教えてくれない場合は「こちらのリクエストを真摯に受け止めて教え方をうちの子にカスタマイズしてくれない」と言って先生を変えましょう。
問題文の使い方
②情報の取捨選択構成練習(線引き等)では短めの文章を問題集などから抜粋して使用。
テキトーでも読めてしまうような易し過ぎる文章を選ばないようにする。
授業回数を重ねて読解ルールと解答技法(消去法など)の説明が進んだら、志望校よりもかなり易しめで記号問題中心の過去問を使うと良いでしょう。
また、読みながら「ここはこういう意味だね」等の内容説明は極力「しない」
内容が良く分からない文章でも独力で情報を取捨選択構成して最低限の点数を取るのが読解技術だからです。
余りに知識教養不足なら事前に数分の補講をする。例えば、文章のテーマに関する通説(説明文読解の前提)、近現代と近代以前の社会の仕組みの違い、外国や昔を舞台とする場合の風習の違い等を教えておきます。
授業の計画が前もって立っているならば、前回の授業の最後に板書して次回までに読んで覚えてくるのを宿題にする。
宿題の出し方
基本方針
出来ない生徒に「お手本通り出来るもの」以上の宿題を出すと細かいチェックや直しが必要になり、授業が宿題対応だけで終わってしまう。
これでは極端な話、宿題を出す→解説→宿題を出す→解説という無限ループに陥って「授業」時間が無くなってしまう。
授業の復習・続き
授業の開始当初は読解のルールそのものを理解記憶することが大切で「解く」宿題は出せません。
授業で「線引き」を行ったなら、同じ文章のきれいなコピー3枚に線を引くのを宿題に出す。
メイン授業として実施しているなら、易しめの読解問題をプラスして、線を引いて解かせる。
このような宿題はやってさえあればOKとします。
この開始当初の時期は独習できる課題(後述)や非常に簡単な(学年が一つ下の問題集など)で学習量を穴埋めします。
授業が進んで解答技法の説明も終わり、読解問題に解答するのが宿題になっている場合は、解答用紙への記入と採点と正しい答えを赤で記入するところまでをやってくるようにする。
記号問題中心の文章を選んでいれば解説はほとんど必要ない(解説が必要な場合は、必要な技法の説明が事前にできていない事が多い)。
大切なのは、忘れた頃に同じ問題を(新品を用意して)もう1回解かせて、今度は100点が取れるかチェックすること。
独習できる課題
あとは、独習できる課題を加える。
A易しい問題集→過去問
授業開始時には、学習量確保と読書体験の代用目的で、一学年下の問題集などテキトーに解けるレベルの問題集の演習と採点まで宿題にする。
授業が軌道に乗ってきたら、授業で扱う問題よりも易しめの過去問1年分の演習と採点を宿題にして得点を記録していく。
B読解公式や解答技法の記憶
授業で作ったノートやカードを「全部」「カンペキに」「即座に早口で」言えるようになるまで反復を厳命する。
「一生懸命やっているが出来ない」生徒さんには、こういう解法の記憶が絶対に必要。
「無理に記憶させなくても、繰り返しやっていれば自然に出来るようになる」というのは、それで出来るようにならない人達を置き去りにするダメ方法論だと感じる。
問題を読んでいる時に、もうひとりの自分がヒントを出してくれる状態(公式の内部化)を目指す。
C知識系の反復練習と記憶
入試までに仕上げる漢字や語句の問題集を決めて宿題に出す。
授業開始当初は、読解に役立つようなものから出題。説明文用に類義語対義語、物語文用にことわざ慣用表現など
授業が軌道に乗ってきたら、問題集の最初からペースを決めて機械的に宿題の範囲が決まるようにして、徐々に生徒に任せていく。
D簡単な作文系
授業開始当初に有効な課題。
抽象具体作文、QBA作文、対比作文(表)、感情作文、変化作文など読解技法の補助になる作文課題を出す。
「作文課題の例」
自分の経験上、生徒の記述への心理的なハードルが大きく下がって、とりあえず何か書くようになる。
Cその他
自分の場合、個別メインで理社を取っていない生徒には、理社の知識の記憶も宿題にする。
この記事を参考に
個別指導塾や家庭教師を効果的に使って、あなたのお子さんの志望校への合格可能性がアップすることを祈ります!
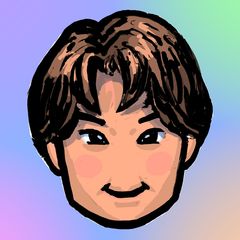 爽茶
爽茶最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事があなたの役に立てたら嬉しいです♪
オリジナル教材のご案内
御三家・早慶付属など難関・人気の中学に合格した2025年度の受験生達から大好評!
分かりやすいのはもちろん、スキマ時間にお子様一人で反復定着できますよ
人気教材はこちら(クリックするとショップ内教材ページにジャンプ)
●歴史 ●時事問題(2025年) ●世界地図 ●世界遺産
■算数(割合、食塩水、売買、仕事/ニュートン算、時計算、すい体 etc)
★理科(月の満ち欠け、星の動き、電流、水溶液/気体の性質 etc)
その他にも社会/理科/算数の教材がございます。興味がある方は公式ストアへどうぞ



コメント